第11回 【前編】社会デザインとIX(インクルーシブトランスフォーメーション)との交差点
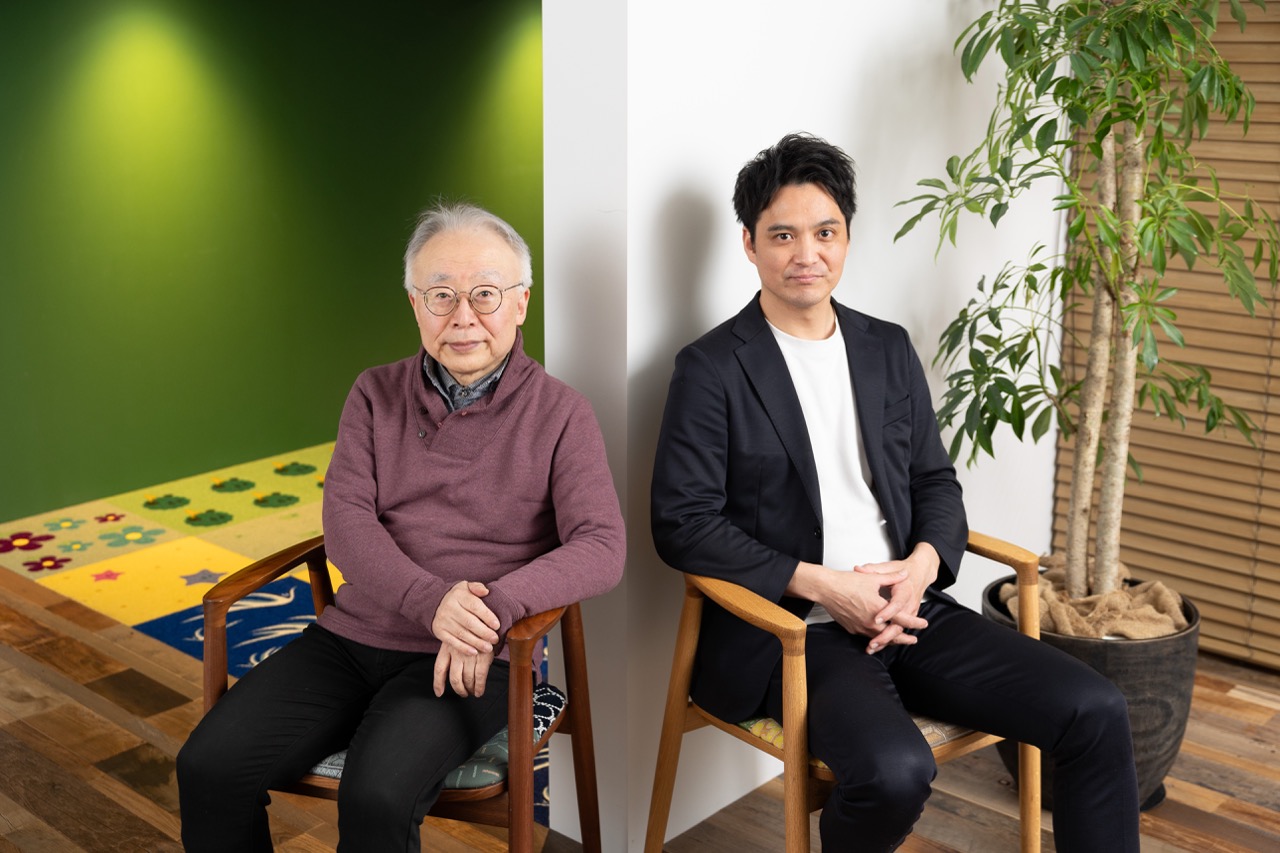
Road to IX
〜 就労困難者ゼロの未来へ 〜
中村陽一氏
VALT JAPANはNEXT HEROを通じて、日本発のインクルーシブな雇用を実現する社会インフラ作りに挑戦しています。その理想実現のため、様々なセクターの皆様と就労困難者ゼロの未来実現に向けて議論を積み重ねていきたく、対談を連載しております。 今回は、社会デザインという概念を日本に根付かせた第一人者、中村陽一先生をお迎えし、「社会デザインとは何か」、そしてその視点から見た現代社会の課題や、IXとの交差点について、深くお話を伺いました。

ゲスト 中村陽一氏
一橋大学社会学部卒業。立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授、同研究科委員長等を経て、現在、立教大学名誉教授、東京大学大学院情報学環特任教授、青森中央学院大学経営法学部特任教授、社会デザイン学会会長。著書に『21.5世紀の社会と空間のデザイン――変容するビルディングタイプ』(共編著)誠文堂新光社、『3・11後の建築と社会デザイン』(共著)平凡社、『日本のNPO/2000』(共編著)日本評論社など多数。
インタビュアー 小野 貴也
VALT JAPAN株式会社 代表取締役CEO
目次
「社会デザイン」とは何か
小野 貴也
(以下、小野)
著書『社会デザインをひらく』(ミネルヴァ書房)を拝読しました。立教大学に「社会デザイン研究科」を設置されたのも中村さんですが、ご著書にもある“社会デザイン”という言葉の定義について教えてください。
中村陽一氏
(以下、中村)
社会デザインを英訳すると「ソーシャルデザイン」ですが、私は「様々な関係性を編み直し活かすこと」と伝えています。「様々な関係性」というのは、人と人、人と地域、人と組織、場合によっては組織と組織などですね。この関係性がうまくつながっておらず、パイプが詰まっているような状態になることで多くの社会問題が生まれる。それらを新たな組み合わせで編み直す、という発想です。さらに「デザインの目的は何か」というと、人々の幸せ(well-being)を実現するのが目的です。具体的に何をやるかというと、様々な関係性を調整する行為であり、これをデザインだと説明しています。
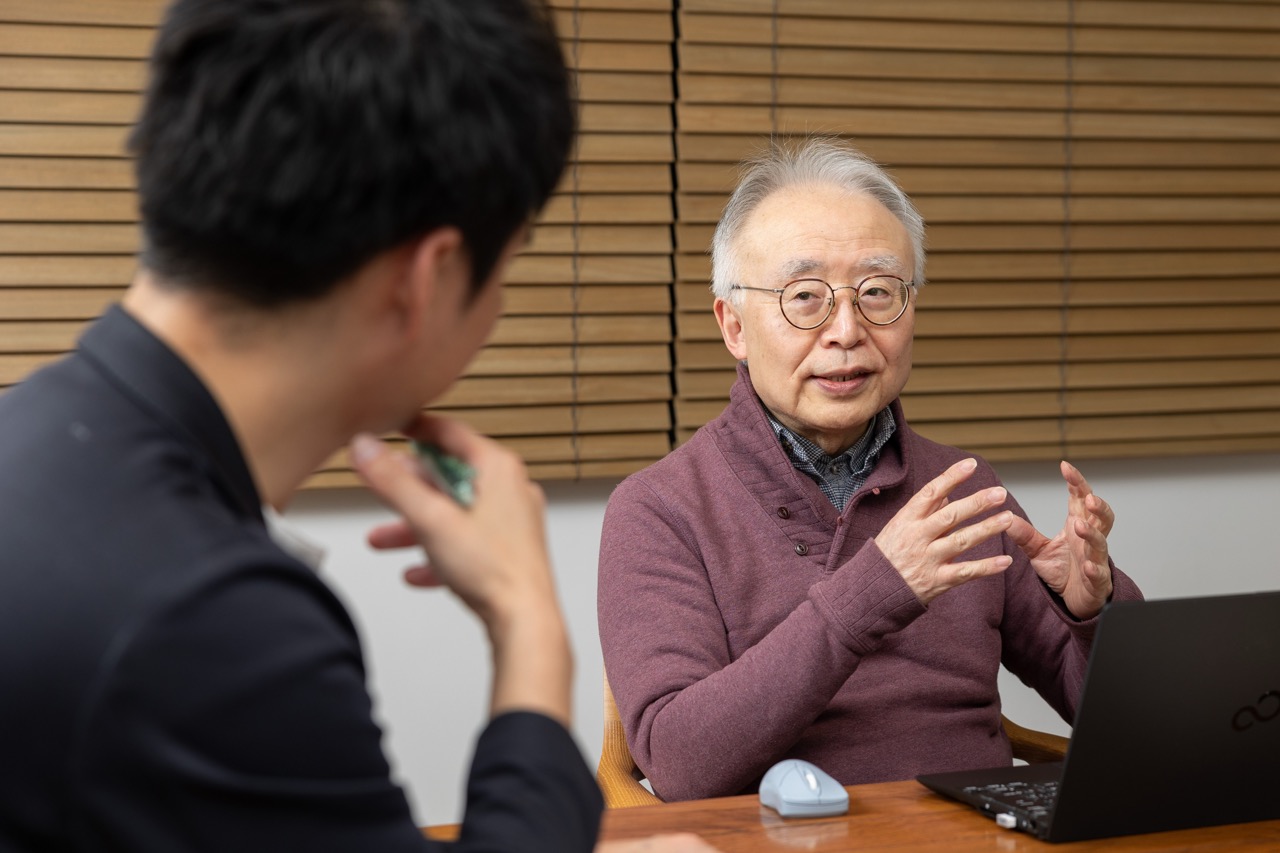
小野
今のお話から、社会運動というのも、関係性を調整する行為ではないかなと思いました。それでいうと、社会運動は「意志」で起こせるものなのか、あるいは自然発生的に起こるものなのか。それについてはいかがでしょうか。
中村
社会運動そのものは、最初は社会問題を公共的な発想から解決しようという人たちが少数で現れます。現代社会は我々が知らない社会問題が数多くあり、そこで社会運動があり、メディアが伝えて初めて、「そういう問題があるのか」と気がつく。リーダーは大切ですが、意志ある人だけで何かできるかというとそうではなく、リーダー以上に理解し、フォロワーとなった人が多くの人に発信していく。そういう人たちが現れてくるかどうかが鍵になると思います。「ソーシャルデザイン」というときは、ソーシャル「な」デザインのことで、形容詞であるので「少し世の中をもう少し良くしましょう」という取り組みだと思うんです。一方の「社会デザイン」というときは「社会をデザインする」ということですから、先述のように、いろいろな関係性を編み直し、より良い方向に持っていく。つまり、社会を構造的なところから変えていきたいというのが社会デザインなのだと思います。ですから「ソーシャルデザインから、社会デザインへシフトしていきたい」。そう考えているんですね。
「社会性、事業性、革新性」+関係性
小野
私も、労働市場の構造を変えていきたいと思っています。就労困難者が1,500万人いる一方で、労働人口減少によって労働力が1,100万人足りなくなり、供給が必要になっている。労働市場の不均衡というときに、社会や労働市場を「良くする」だけではなくて、「変えなければいけない」という想いを持って事業に取り組んでいます。ですから私たちは就労困難者だけではなく、企業側をはじめ資本市場の領域も変えていくことにチャレンジしており、経済性を重要視しています。NPOにおいては、当然経済性が大事にされていると思いますが、非営利要素も当然ながら同じように大事にしている。NPOの役割についても、中村先生にお伺いしたいです。事業性、社会性、そして変革性。現代社会において、この3つをどのようにバランスさせることが重要でしょうか。
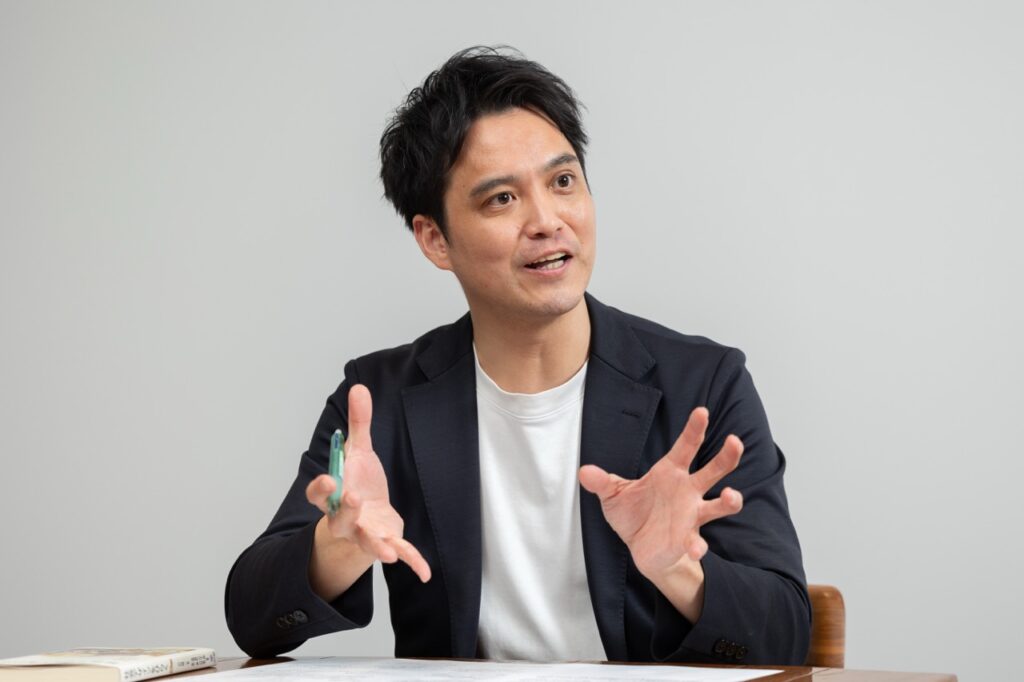
中村
社会性、事業性、革新性は、厳密に言うと、ソーシャルビジネスについていわれていることですね。NPOもその中に入りますが、まず社会性は民間企業により意識してほしいところです。民間企業は事業性がベースにあるので、プラス社会性をどう考えていくか。逆にNPOも含めた非営利の組織には、事業性を意識してほしいところです。革新性は、単に社会を良くするだけではなく、社会を変えるという、構造的、論理的な視点を持ってほしい。もう一つ付け加えたいのは、繰り返しお伝えしている関係性で、私は「つながりを編み直すワーク」という言い方をしますが、社会的な事業活動こそ、今後重要になっていくと思います。非市場経済は、「贈与の経済」「ボランティア経済」とも言われ、人の相互的な行為によって疑似的に経済が成り立つものです。そして市場経済と非市場経済との間には、半市場経済があります。私が考えている社会デザインビジネスは、この3種を行きつ戻りつしながら、事業や活動、あるいは運動が進んでいくものと捉えています。「社会性、事業性、革新性」にプラスした「関係性」までを含めて、ですね。
小野
私たちは経済性を重視しながらも、非市場経済の要素にも取り組んでいると思っています。資本主義の中心にいる投資家やベンチャーキャピタルの支援を受けて、新しい構造やインフラを作ろうとすると、どうしても経済性に寄る必要があります。しかし、実際のオペレーションでは、経済性だけでは回らない部分があるんです。例えば、就労困難者の方々のスキルが向上しないと、業務を納品できません。経済性を優先すれば、すでにスキルの高い人に仕事を依頼した方が収益性は上がります。でも、それでは就労困難者に仕事を提供できなくなる。そうなると、「そもそも、私たちの会社は何のために存在しているのか?」という問いに行き着きます。だからこそ、「市場経済・非市場経済・半市場経済」を行き来することが大切なんだと、あらためて実感しました。言葉にするとシンプルですが、実際に意識して実践するのは難しいですね。
中村
事業を続けるには、効率性や生産性を高める発想が欠かせません。しかし、市場経済の考え方に偏りすぎると、おっしゃるようにふと「自分たちのミッションと合っているのか?」と疑問が生じることがあります。NPOの例でも、経営やマネジメントの重要性が叫ばれ、事業としての側面が強くなりました。それ自体は良いことですが、効率やコストパフォーマンスばかりが重視されるようになり、「そもそも何のためにNPOをやっているのか?」という問いが生まれるようになりました。やはり、市場経済と非市場経済を行き来しながらバランスを取ることが大事なのだと思います。
突破力とは、社会を変えようという意志
中村
昨年、トヨタの本社で講演をしましたが、「社会性というものを考えたい」と、最近は社員の方たちの気持ちも変わっています。大企業の中でも、社会性と事業性のせめぎ合いで悩んでいる人たちが増えているのは、NPOなどのソーシャルなセクターの人たちとどこかで通底するものがあって、興味深いと感じました。
小野
NPOと事業性というお話から、ご著書にもあった、事業性だけではない「突破力」という言葉が印象的でした。突破力とはどんな要素から生まれるものでしょうか。
中村
この言葉には、『世界を変える偉大なNPOの条件』(ダイヤモンド社)という本との出会いがあります。優秀なコンサルの著者たちがアメリカのNPOを分析するにあたり、「素晴らしい業績を上げているNPOはマネジメントやミッションの土台がしっかりある上で経営をしているに違いない」という仮説で望むのですが、見事に裏切られます。実際に組織運営を見ると混乱していたり、意外なNPOが実は成果を上げている。「レバレッジ理論」というのはテコの原理ですが、そういうNPOは小さなリソースである自分たちの力を、テコを活用して大きな成果につなげていたわけですね。ではそのテコは何かというと、外部との幅広いつながり。ネットワーキングです。そこから得たものを自分たちのアイデアとうまくつなげる力がすごいんだと、著者たちは気が付く。このことを、私は「突破力」と表現しました。もう一つは「ネットワーク力」。教科書的なマネジメントでは、組織基盤強化とよく言われますが、もちろんやらないよりやった方がいい。けれども、その理想的なマネジメントをして組織基盤ができたからといって、良い事業を行い、社会を変える成果が出るかというと、私は必ずしもそうではないと考えます。そこには、中心になって動く人たちの「社会のここを何とかしたい」「何が何でもやる」という気持ちと、外部とつながることで可能になるのです。

小野
NPOに限らずスタートアップの世界でも、突破力という考え方は、ど真ん中にあると思います。事業を伸ばすとか、事業を作り上げるなど、ゲームチェンジを起こそうとするときには正解はないものですね。
中村
教科書的な事業経営をしたからといってうまくいくことはない。どこかで、夜も寝られずに悩むことが出てくるわけですよね。そのときに「えいやっ」とやれるかどうかは大事なことで、その裏付けは「自分は絶対これを達成する」という強い意志だと思うんですね。実際に悩んで決断をして、踏み出した人たちの話や経験を共有することが、こういうサードセクターの世界では大事だと思います。
小野
物事を始めようとした「Day1」から、突破力を持っている人というのは、極めて少ないように思います。先ほどおっしゃっていた、「事業性、社会性、革新性」+関係性ですが、関係性は、自分にないものを持っている方から、それをどう吸収していくかという考え方ですよね。関係性を作る上で、非常に大切ではないかなと思いました。
対談の後編では、
- 企業がNPOと連携・共創する社会
- ESG投資と企業の姿勢
- DSX(デジタル・ソーシャル・トランスフォーメーション)の実現
について語ります。
当対談は音声でもお楽しみいただけます。下記のSpotifyよりご視聴ください。

